センター生物からみた過去問の重要性と
共通テスト対策
- O講師
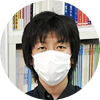
- 著者
- 兵庫県出身。公立高校では文系。その後理系に転向し、北海道大学工学部卒業・大学院中退を経て、札幌医科大学医学部に進学。主要5教科では地理以外は全て指導経験があります。高校生に関しては、これまで100名以上の生徒を指導しています。
令和2年7月現在、シニアの教室で多くの高校生を指導中。 - 内容
- 来年の1月からセンター試験に変わる大学入学共通テストが実施されますが、その対策の仕方や二次試験対策までが丁寧に述べられています。
「大学受験マークプレテストで32点を記録」
これが、いかに危機的状況にあるかということは、承知していただけるかと思う。この状況から僕がセンター試験本番で89点を取ったことから学んだ「センター試験の過去問の重要性」を基に、2020年度から始まる共通テストへの、センター試験の過去問の生かし方について私見を述べる。
1. 生物のセンター試験過去問演習で感じた違和感
上記プレテストの結果を受けて、勉強法を見直した(12月~)。具体的には、講義中心の勉強から、センター試験の過去問演習中心の勉強に変えた。過去問を分野別にまとめた問題集を買い、演習を通じて知識を整理しようとしたのだが、解いていくうちに、予想以上に解けないため、まずは解説を読むことが学習の中心になった。
結果的に、この勉強法の転換が成功の大きな要因になったのだが、解説を読む際、
「なぜ、ここまでは知っていることとするのか」
「この実験考察は、こういう解釈として、了解するしかないのか」
と思うことが多々あった。
これらは、模試の復習では感じなかったもので、「センター試験の独特さ」を感じた。結果的に、僕は勉強の目的を、「演習を通じて知識を整理しようとすること」から、「センター試験の“癖“を把握し、理解すること」に重点を置き換えて、問題集の2周目を行った。
問題集は赤ペンだらけになったため、年明けに同じものをもう一冊買い、今度は自力で解いていくことで、理解したセンター試験の考え方を「再現」するようにした(3周目)。センター試験本番の結果は、今までの模試での最高点をも大幅に上回る点数であった。
2. 共通テストの過去問は2回分の「試行調査」のみか
昔、東京大学を目指していた文系の友人が「国語はどんな問題にも通じる対策がある」という趣旨の話をしていたのだが、元文系だが国語は出来ないという「なんちゃって文系」だった僕には違和感があった。「センター試験の国語と模試の国語は、違う。センターの対策にセンター試験の過去問は使えても、模試はそこまで使えない」と感じていた。センター国語、特にセンター現代文については、過去問と模試に違いがあり、したがって過去問でしっかり対策することが必須という話は、ほとんどの方に了解していただけるものと思う。マーク模試の復習を、国語についてはやらなかった方もいると聞くが、僕もそうだった。現代文は文章を読んで、「どんな話だったか」を把握するくらいで、あとは古文漢文の単語・文法を確認する程度で、復習は終えていた。
センター試験の英語についても同様のことが言えて、模試の英文を復習するときは、英単語を覚えることと、英作文に使えそうな表現を「借りる」程度で済ませていた。
先述した生物の勉強の際に感じた違和感の正体は、これだ。つまり、国語、英語に加えて、生物についても、センター試験の過去問での対策が必須だということだ。
もちろん、過去問と同じ文章が出るわけではない。しかしながら、選択肢の作り方・切り方、上述した「実験考察の癖」は、間違いなくセンター試験独自のものがある。
今年度から、紆余曲折があったうえで、共通テストが導入される。参考とされるのは、先駆けて行われた2回の試行調査の問題で、これらを充分に研究することは必須である。そのうえで、各予備校が行う模試や、出版される模擬問題集で演習していくことが勉強法となるが、センター試験の過去問も利用することをお勧めする。具体的には、英語や現代文について、選択肢の作り方や切り方をセンター試験の過去問で学ぶということだ。他方、英語の設問の作り方は、共通テストでは複雑化しているので、共通テストの模試や模擬問題集で学ぶ。設問や選択肢は、本文とは異なり短い文の中に多くの情報が含まれるため、文法への理解の重要性はむしろ増している。共通テスト英語リーディングは、先刻話題になった4技能(リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング)のうちの、リーディングに特化した試験という位置づけだが、文法知識は問われないとは一言も言われていない。先生が文法を軽視している学校の生徒は、特に気を付けてもらいたい。その動詞が、どのような文型で使われているか、単語帳の例文や文章の構造分析を通して理解できるよう、品詞についてもしっかり押さえるべきだ。
理科に関してはセンター試験と比べ、実生活に即した内容になる。ここでもまた、センター過去問での対策は、有効になる。生物の知識や実験考察について述べてきたが、化学や物理についても、センター試験独特の癖は、やはり存在する。多くの生徒をみてきたが、模試では点数が取れている一方で、センターの過去問では成績が伸び悩んでいる生徒が少なからずいたので、この感覚は一定の正しさを持つであろう。2015年から、理科のセンター試験と二次試験の試験範囲が同じになったことで、「理科は二次試験の対策をすることで、センター試験も乗り越えられる」という意見が散見されるが、鵜呑みにすべきではない。理科が得意である生徒以外は、少なくとも生物についてはセンター試験の過去問で十分に対策してほしい。そのうえで、試行調査、共通テストの模試や模擬問題集で演習をする。
まとめておくと、僕が今年受験するならば
英語、国語、そして理科(生物以外にも有効と感じているので、あえて理科と表記する)は、
- 模試、模擬問題集で多くの文章(特に英文)に触れる、複雑化した設問の作り方に慣れる
- センター試験過去問で選択肢の作り方や切り方、理科は実験考察の癖を充分に研究する
- 試行調査の研究は絶対
という目的意識を持って勉強する。戦略がとても大切だ。
3. 共通テストで大きく変わるであろう、数学への対策
共通テストで最も対策が難しいのは、実は数学である。試行調査で平均点が低すぎるため、試行調査のような出題方法がどこまで維持されるかも不透明だという意見もあるようだ。やはり試行調査をしっかり研究したうえで、模試や模擬問題集で練習しつつ、ここでもセンター試験の過去問を使うことになる。
センター試験には、やはり癖はあり、作成する組織が大きく変わらないということは、作成者が大きく入れ替わったとしても、やはり彼らもセンター試験の過去問は参照するはすだからだ。例えば、二次関数で有名なX軸との共有点の個数の求め方は、頂点のY座標からグラフで考えさせる誘導がついていることが多く、判別式は別解になり続けている。関数の問題であるから当たり前なのだが、この「別解を考える習慣はつけておくべき」ということが、試行調査から伺える。
ベクトルの直線上の点についても同様で、厳密には様々なアプローチがあるのだが、センター試験で好まれる表現方法は、ある程度決まっている。したがって、そこには別解が存在するということだ。
二次試験の例ではあるが、試行調査の「別解を意識させる」方針について、「図形問題」を例に解説したい。他の記事にも書いたことではあるが、再度読んでほしい(O講師NO2参照)。
図形問題に苦しむ生徒は多いと思う。予備校の夏期講習などで「図形問題」に焦点を絞った講座が少なからず存在するのも、そこに需要があるからだろう。僕のアプローチの仕方を記載しておく。
まず、「図形」をどこで学んだか、思い出す。読んでいる方々も、思い出していただければ幸いだ。数学Aの「平面図形」数学Ⅱの「図形と方程式」は、名前に「図形」が入っている。そういえば数学Ⅰの三角比も、正式には「図形の計量」だったな。数学Ⅲの「式と曲線」も「図形と方程式」のようなことをしていたな(円と楕円の関連性など)。数学Bのベクトルも「平面ベクトル」「空間ベクトル」があった。「平面」と名付けられているから、これも図形だな、といった具合。中学でも1年で「平面図形」「空間図形」を、2年で「合同と証明」「三角形と四角形」、3年で「相似と証明」「三平方の定理」を学んでいる。思い出して、これらの単元で何を学んだか、教科書の目次をみて、思い出してほしい。知識を「道具箱」のように頭のなかで整理しておく。その「どれを使ってもいい」という意識を持っておく。意外と「やってはいけないことは少ない」。これで、ベクトルの別解がメネラウスの定理であっても、さほど驚かないようになるし、頭に浮かぶようになる。
3. まとめ
共通テストについて戦術を立てて目的意識を持ちながら対策をし、一方で二次試験は大きな変更はないので、早めに完成させておく。「受験の天王山は夏」と言われるが、2020年度については、夏の前に勝負を決めるくらいの意識で、二次試験の勉強を行うことで、共通テストも余裕をもって対処できる。万が一、新型コロナウイルス感染症の影響で入試日程が延期になったとしても、条件は皆同じであるから、延期した分、学力レベルは上がる。
特別な能力やひらめきは必要ではないし、今の自分の実力の無さに落ち込んでいるのであれば、それを重くとらえる必要もない。正しい努力の仕方はあって、戦術でカバーすることによって、現時点で存在する実力差は、大学受験の範囲では十分埋められる。基本を大切にしつつ自信を持って、努力と創意工夫で頑張ってほしい。
以上
-
- O講師の
数学偏差値40台から
北海道大学医学部に合格した勉強法 - 数学では、何に重点をおいて学習すれば良いかが明確に語られており、数学の学習に不安のある生徒にとっては、とても役立つ内容だと思います。偏差値40台からでも十分挽回できます。
- O講師の
-
- O講師の
北大英語で8割が取れる勉強法 - 大学入試で、英語を得点源にする勉強法がわかりやすく書かれています。南高で実テ1位はなかなか取れません。英語が伸び悩んでいる生徒にはとても参考になると思います。
- O講師の
-
- U講師の
物理が苦手な状態から、北大総合理系物理重点1位を取った勉強法 - 物理で得点できない生徒が多い中、物理学習において、何に気をつけて学習していけば良いのかが丁寧に述べられています。物理で受験する生徒にはとても参考になると思います。
- U講師の
-
- U講師の
追試を受けるほどの状態から
数学を得意・武器とした勉強法 - 数学学習において一番大切なのは、「基礎」。著者の一番伝えたいことが、何度も語られています。生徒の皆さんには、単に言葉として受けとめるのではなく、模試の見直し等で実感してほしいと思います。
- U講師の
-
- 鈴木講師の
勉強を楽しむ - とにかく、勉強は楽しみながら進めることが大切で、それができれば自ずと成績も伸びてくる、というのをモットーにしている講師です。いろいろと誘惑の多い現在、勉強よりも楽しいことがいっぱいあって、勉強はとかく辛いものになりがちですが、自身の勉強の楽しみ方が教科毎に述べられています。
- 鈴木講師の
-
- N講師の
北大物理で9割近くの点数で安定する勉強法 - 物理で高得点を取るための方法が、簡潔明瞭に述べられています。
- N講師の
-
- O講師の
センター生物からみた過去問の重要性と共通テスト対策 - 来年の1月からセンター試験に変わる大学入学共通テストが実施されますが、その対策の仕方や二次試験対策までが丁寧に述べられています。
- O講師の
-
- O講師の
受験数学で「頭打ち」から抜け出すために必要な考え方と勉強法 - 数学で飛躍すべき方法論が具体的に述べられています。
- O講師の
-
- H講師の
物理を0から得意科目に - 一般的に取っ付きにくい物理の学習において、大切にすべきこと、解き直しの重要性、オススメの問題集などが丁寧に述べられています。
- H講師の
-
- T講師の
化学を得意に - 化学が大得意と言うだけあって、化学を学習する上でおさえるべきポイントが、単元別に明確に述べられています。化学に不安を感じている生徒、伸び悩んでいる生徒は、ここに書かれていることを、今日から実践して欲しいと思います。
- T講師の
-
- E講師の
「自分との闘い」と「物理」 - 医学部受験に向けての甘えや不安の克服、そして、物理の得点を大幅にアップさせた勉強法が、具体的に語られています。
- E講師の
-
- M君の
難関私大入試の英語の勉強法 - 慶應大学はじめ難関私大入試のための英語の勉強法が、丁寧に述べられています。また、使用教材についても、余すところなく紹介されています。
- M君の
-
- T講師の
数学で高得点を取るために
(二次試験対策) - 一般的に言われる「数学はパターンである」の真意について述べられており、数学で高得点を取るための方法論として、とても参考になる内容です。
- T講師の
-
- M君の
おすすめの化学の勉強方法 - 化学の勉強法、得点源にするための方法論が、丁寧に述べられています。化学が苦手な生徒、伸び悩んでいる生徒には、とても参考になる内容だと思います。
- M君の
-
- M君の
物理学習に対する心構え - 物理はどのように勉強していけば良いのか、何を意識して取り組めば良いのかが、問題集の取り組み方なども含めて、わかりやすく書かれています。物理を苦手にしている生徒、あるいは、苦手にはしていないが伸び悩んでいる生徒には、とても参考になると思います。
- M君の
-
- Uさんの
偏差値33からの大逆転 - これだけ遅くからの勉強で、北大に現役合格した話を聞いたことがありません。中学の復習からスタートした大学受験への取り組みが、詳細に述べられています。目標を諦めかけている生徒、もうダメだと思っている生徒には、とても参考になります。
- Uさんの
-
- K・Yさんの
数学を武器にする
(トップ高校での数学学習法) - 公立のトップ高校での数学の取り組み方・克服の仕方や、普段の学習方法などが説明されています。特に、授業の大切さ、復習の必要性が述べれられています。トップ高校の生徒は必読です。
- K・Yさんの
-
- M君の
数学学習上のヒントについて - 数学対策について、実践的な内容がちりばめられており、難関大学の数学対策にはとても参考になる内容です。特に、検算の大切さ、難問が出題された場合の対処法は必読です。おすすめの参考書も記載があります。
- M君の
-
- Sさんの
英語の長文読解のヒントについて - 英語の長文読解のヒントだけではなく、英語の学び方についても、やさしく丁寧に触れられています。高校生の方だけではなく、中学生の方にも参考になると思います。
- Sさんの
-
- H君の
数学のすゝめについて - 数学の得点アップのための方法論が丁寧に述べられています。
計算力対策、公式の覚え方は、納得です。高校生の普段の学習シュケジュールはとても参考になります。受験で数学が武器になります!
- H君の
-
- K君の
現代文の勉強法について - 評論文対策についての勉強法が丁寧に述べられています。国語の点数は伸びないと諦めかけている高校生には必読です。
- K君の
-
- K君の
化学の勉強法のヒントについて - 化学は暗記だけの科目ではありません。参考書は複数、問題集は一冊を使う!化学が苦手な高校生だけでなく、化学が得意な高校生にも参考になります。
- K君の
-
- A君の
物理学習のヒントについて - 効率の良い物理の学習法について丁寧に述べられています。物理が苦手な高校生、物理が嫌いな高校生は是非読んでみて下さい。問題集についても触れられています。
- A君の
-
- T講師の
人工知能の研究について - 大学入試には直接結びつきませんが、大学院での研究テーマである「人工知能」の内容がわかりやすく書かれ、最近の応用分野にも触れられています。人工知能に興味を持つ生徒がどんどん出てきて、大学進学を目指して欲しいと思います。
- T講師の
- お気軽にご相談ください。お電話お待ちしております。
-
各種お問い合わせ(日祝除く10~21時)
0120-973-595
